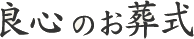お葬式はお坊さんのお経で!!
お布施が、格安(2万5千円〜)の
「良心のお葬式」
料金・低価格・安心・信頼の
ご葬儀の相談

✆ 0120-44-24-24 072-772-7422
顧問の元警察官・現僧侶が無料相談
携帯 090-1588-2757(24時間対応)
現代の習俗や文化は仏教が起源
日本に仏教が伝わったのが、536年とされています。
6世紀末に、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化が生まれました。

聖徳太子 
仏 
葬儀・葬式
現代の葬儀は、仏教を起源

浄土に旅立つ 
古来からの各宗派
現代に伝わる儀礼や習俗は、仏教を起源としているものが多くあります。
その代表が葬儀・葬式です。
この葬儀・葬式は、死者が戒名(法名)を頂いて、仏(ブッダ)の弟子となり、浄土へと旅立つ儀式です。
死者は、浄土に導かれ49日後に悟りを得て、仏に成る(成仏)と言われています。
現代の日本に於いては、古来からの宗派はいずれも死者は仏に成ると言われています。
葬儀以外で、仏教が起源のもの
葬儀以外で、仏教を起源としているものに、お彼岸やお盆があります。
このお彼岸やお盆は、仏となった先祖を偲び、同時にこの世にいる自分たちを守ってくれるように祈る行事です。
お坊さんの読経(お経)での葬儀
「僧侶のお経」は、故人をあの世へ導く
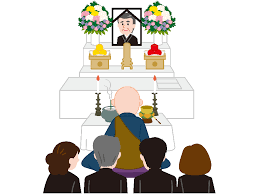
葬儀=あの世に送る 
お経は、あの世に導く 
浄土へ旅立つ
日本は仏教国です。
人が亡くなれば、最初に「枕経(まくらぎょう)」経をあげます。
ですから、最初にお坊さんに連絡しなければなりません。
昔から葬儀(お葬式)は、お坊さんのお経をあげてのお葬式でした。
お葬式でのお経は、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があります。
故人は浄土へ旅立ち、仏となるのです。(成仏)
「僧侶の読経(お経)」は、心を癒す
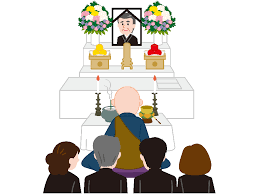
お坊さんの読経での葬儀 
身内や参列者の心を癒す 
仏を信じる
葬儀・お葬式とは?
葬儀・お葬式とは、遺族、友人・知人が故人を偲び、あの世に送るための儀式です。
又、遺族など参列者が、お坊さんのお経によって、心を癒す儀式なのです。
仏教と葬儀の結びつき

聖徳太子 
仏式葬儀 
僧侶読経葬儀
日本では、538年仏教が伝わり、6世紀末に聖徳太子が仏教を国つくりの基本としたことから、様々な仏教文化が育まれ、儀礼や習俗が確立されていきました。
その代表格が葬儀です。
※葬儀と仏教の参考⇒(聖徳太子と仏教)
平安時代には、貴族の葬儀が寺院で行われるようになりました。
この頃に、葬儀と僧侶とお経が結びついたと考えられます。
葬儀社手配と僧侶手配は別々に依頼

僧侶の手配料 
お布施内に手配料(紹介料)
葬儀は葬儀社に依頼し、葬儀の時のお経は、お坊さんに直接依頼しましょう。
葬儀社などにお坊さんの手配を依頼すると、お布施に「手配料(紹介料)」が含まれていることが大半です。
葬儀と戒名

極楽浄土 
戒名(法名)
戒名とは、お釈迦さまの仏弟子(ぶつでし)になった証として与えられる名前のことです。
本来、戒名を授けられるということは、厳しい戒律を守り仏門に入って修行をし、経典を勉強した人の証として授かるものなのです。
戒名は、元々は生前に与えられるものですが、現代では、大半が亡くなった時に授与されます。
故人が戒名を授けてもらう理由は、迷うことなく極楽浄土へ行くという理由からです。
浄土真宗では戒律がないため、戒名ではなく「法名(ほうみょう)」と言います。
現在、日本にある戒名は日本独自のもので、戒名が言われだしたのは、江戸時代と言われています。
葬儀とお坊さんとお経(読経)

葬儀 
葬儀の時のお経本 
お坊さんのお経(読経)
昔からお葬式は、お坊さんがお経をあげて執り行っています。(お坊さんの読経)
お経とは、お釈迦様の大切な教えがまとめられている文書(聖典)のことです。
元々は、故人に向けたものではなく、生きている人に向けて作られました。
※参考資料
葬儀など、直接お坊さんに依頼!!

葬儀の時の僧侶の読経 
お寺は不要 
信頼出来るお坊さん依頼
お寺との付き合いが無くても、葬儀などで困ることはありません。
檀家制度は、江戸時代の悪しき慣習

江戸幕府が檀家制度を確立 
檀家制度で
お寺が民衆を管理
お寺が民衆の身分を保証
現代は、檀家制度が崩れ、お寺との付き合いが無いのが当然
近年は檀家・門徒制度が崩れ、お寺とのお付き合いをしたくないという方が増えてきております。
この檀家・門徒制度は、遺物であり悪しき制度だと思います。
読経(どきょう)
「読経」とは、お経を声に出して読むことです。
記されている内容を覚えるため、もしくは人に教えを説くための行為です。
通夜や葬儀のときに亡くなった人の仏前で読経しますが、これは参列している親族や近しい人に説法するという意味もあります。
枕経(まくらぎょう)は、仏さまに「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」というお礼のお経です。
お経の内容
お経は、お釈迦様から伝えられた教えを弟子たちが再編したものです。
「経典」や「仏典」とも言われます。
当初は口頭で伝えられましたが、後に文書化されました。
お経は、大別して経蔵、律蔵、論蔵の3つに分けられます。
これをまとめて、「三蔵」と呼びます。
三蔵に詳しいお坊さんを「三蔵法師」と呼びます。
お経のそれぞれの内容を見ていきますと、「経蔵」は、お釈迦様の教えをまとめたものとなっています。
「律蔵」は、弟子として守るべき規則をまとめたものとなっており、道徳、生活のことなどが書かれています。
「論蔵」は、経蔵と律蔵の2つを分析して、注釈や解釈がつづられています。
お経の役割
お経は、お釈迦さまがこの世を生きている人が幸せな道を歩めるようにと、作られまとめられたものです。
心の苦しみと向き合い続けたお釈迦さまが、人々に伝えたアドバイスのようなもの、と考えればわかりやすいかもしれません。
葬儀で読まれるお経の役割

葬儀の時のお坊さんの読経 
お経は、故人を
あの世に導く
お経は、遺族などの心を
癒す効果
葬儀で読まれるお経には、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があります。
そして、大切な人を亡くして心を傷めている遺族や参列者を癒す役割も果たしています。
葬儀とお経⇒葬儀
お経を作成したのはお釈迦様の弟子たち
お経は、教えを説いてもらったお釈迦様の弟子たちにより作られました。
お釈迦様が亡くなったのは諸説ありますが、紀元前5世紀頃と言われており、この頃にお経の原型も生まれたと考えられています。
弟子たちは各地から集まり、それぞれが覚えている限りの教えをその場で共有しました。
弟子の中でもお釈迦様の従者であった阿難は、お釈迦様から最も多く教えを聞き、それを記憶していたとされています。
お経が日本に伝わったのは500年代
お経はインドから中国、朝鮮へ渡ったのち日本へと伝わりました。
漢字で記されているものが多いのは、中国で漢訳されたものが多いからです。
日本に伝わったのは奈良時代(500年代)であるとされています。
これも諸説あり、朝鮮からの渡来人が既に伝えていたという話もあります。
葬儀の時の合掌・礼拝

合掌 
礼拝 
葬儀
仏式葬儀で、お葬式の最初に行われている「合掌」、「礼拝(らいはい)」ですが、これらの動作にもきちんとした意味があります。
合掌(がっしょう)
顔や胸の前で、左右の手のひらを合わせる動作が「合掌」です。
合掌は仏様を信じていることを表する動作の1つです。
右手は仏様そのものであったり、悟りの世界であったりします。
そして左手は「自分」です。
通夜や葬儀の場では、仏様と自分(衆生という)が一体となって、故人の成仏を願い、仏さまに故人の今後を託す気持ちを表現しています。
礼拝(らいはい)
「礼拝(らいはい)」は、合掌の姿勢で上体を45度くらい前方に傾けて、礼をして、ゆっくりと上体を起こす動作です。
礼拝には、お礼をするといった意味や感謝するなどの意味があり、祈ることではありません。
また礼拝は、挨拶にも使われます。
私達は昔から、お経をあげての葬儀

亡くなればすぐに枕経 
葬儀の方法は3つ 
葬儀に於いてお経をあげる仏式葬儀
亡くなった時

死亡 
清拭(湯灌) 
出来るだけ早く
枕経をあげる
| 枕経(まくらぎょう) 枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。 勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。 枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。 臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。 死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。 故に、枕経と言います。  |
| 檀家・門徒制度とは、 徳川幕府が民衆を管理するために作った制度で居住地にある寺院を旦那寺として、民衆をその寺の檀家となることを定めたのです。 徳川幕府は、仏教を国教として仏教を人民統治に利用したのです。 旦那寺は、檀家の葬祭供養を行うほか、檀家の身分を保証したのです。 檀家には、旦那寺に布施を施す義務が課せられました。 |
仏教の伝来
お釈迦さまの降誕~苦行~入滅

マーヤー夫人 
お釈迦さまの誕生
降誕
お釈迦さまは、シャカ族の出身です。
シャカ族は、カビラビャットゥを首都とする所です。
現在のネパール領タラーイ地方に存在した小さな国の種族でした。
カビラとは、「赤い土」という意味で、年中山頂に雪が積もるヒマラヤ山の麓に存在したところです。
この地は、ガンジス河の支流であるローヒーニー河に面しており、水田耕作に適していた土地であったようです。
お釈迦さまの父はスッドダナーと言われていますが、お釈迦さまの兄弟に白飯や「飯」という名の方々がいましたので、シャカ族は「稲作」を主とした部族だったと思います。
シャカ族は、「稲作」に優れていたようですが、軍事力はさほどなく、カビラビャットゥの西南にあった大国コーサラ国に隷属をしていたと言われています。
当時のインドは、サービャティを首都とするコーサラ国とラージャガハを都とするマガダ国が二大強国で、弱小の国はいずれかの陣営に属することによって存続していたようです。シャカ族は、コーサラ国に属していましたが、お釈迦さまの晩年、コーサラ国によって滅亡させられました。
お釈迦さまは、スッドダナーとマーヤー夫人の子供として生まれましたが、マーヤー夫人は隣国コーリア族の出身であったと伝えられています。
王とマーヤー夫人のお二人は、長い間子供に恵まれんでした。
当時は厳しいカースト制度があり、バラモンやクシャトリヤは、インドの法典である「マヌ法典」の規定に縛られて生活していたわけですが、その聖典には跡継ぎをもうけることが家長に課せられた最大の義務であることが定められていました。
ですから、王は家長としてお釈迦さまが生まれるまでは辛い立場にあったと考えられます。
マーヤー夫人は、ある夜、純白の象が胎内に入る夢を見、間もなく懐妊となりました。
臨月が近くなって、夫人は実家のコーリア国に向けて旅立ちました。
法典に、お産は実家でという決まりがあったからです。
ルンビニー園を過ぎるころ、マーヤー夫人は急に産気づき、お釈迦さまが誕生したのです。
仏伝によれば、ルンビニーの花園で休憩中、マーヤー夫人がアショーカ樹の花房を折ろうと右手を挙げた瞬間、右の脇からお釈迦さまが誕生したということです。
このことは、通常と異なる表現によって、お釈迦さまが偉大なる人物である、ということを伝えようとしたことが窺えます。
只、尋常なお産ではなかったことは確かだと思います。
産み月より逆算して実家に帰省したのですから、旅の途中で早産であったと同時に、旅の途中の出産は難産であったと思慮されます。
マーヤー夫人は、お釈迦さまを出産後、すぐにこの世を去りました。
マーヤー夫人は、お釈迦さまの誕生より7日目に亡くなったと伝えられています。
お釈迦さまは、シッダッタと名付けられマーヤー夫人の妹のマハーパジャパティーによって養育されました。
父王は、仙人にお釈迦さまを見てもらいましたのですが、その仙人が言うには、この子(お釈迦さま)は、「32の偉大な相を備えている。
家にあれば、転輪聖王となり、出家すればブッタとなるであろう。」と聞かされ、王は喜びとともに不安を感じたと言われています。
王子(お釈迦さま)は、雨期・乾期・冬期を快適に過ごせるように3つの宮殿が与えられました。
母(マーヤー)の死は、お釈迦さまの人格形成に大きな影響を与えたようです。
お釈迦さまは、いつしか人々から離れ、静かに瞑想することを好み、孤独が好きな少年に成長していきました。
天上天下唯我独尊 釈尊が(お釈迦さま)が誕生と同時に七歩歩まれ、右手で天を指して「天上天下唯我独尊」と言われました。 この言葉は、この世界に我よりも尊いものはないということで、後に悟りを開かれる釈尊の尊さと、迷いの世界にとどまっている衆生の苦しみに対する釈尊の救いをあらわしたものです。 |
学生期
マヌ法典では、人生を学生期・家住期・林棲期・遊行期に分けます。
当時の学生期は、師について学問・武芸を学び、家住期は、結婚して家業にいそしみ、後継者を育て、林棲期は、森に入って修行し、遊行期は、あらゆる執着を離れて各地を遍歴することが理想とされていました。
少年(お釈迦さま)は、規定により入門式を受け学生期に入りました。
それぞれの師につき学問や武芸を習ったシッダッタ(お釈迦さま)ですが、武芸・学問の分野で非凡な才能を示し、しばしば教師を驚かせました。
シッダッタ(お釈迦さま)が7歳の頃、農耕初めの祭式が執り行われることになり、シッダッタ(お釈迦さま)は、父王や大臣とともに出席し、農夫たちが鋤や鍬で大地を耕す様子を見物することになりました。
その当時の情景としては、
春の遅いインドでは、花は一斉に咲き、陽光に野にも山にも生命の息吹が満ち溢れ、吹き渡る風は心地よく大地の香りを運んできます。
春ののどかな光景が、シッダッタの眼前に広がっていました。
そのような中、一鍬一鍬に心を込めて大地を耕す人々の姿がありました。
皆の額には、汗が美しく輝いています。
彼らが鍬を振り下ろして掘り起こした土の中に、未だ冬の眠りから覚めやらぬ小さな虫がいました。
その虫を見つけた小鳥が、その虫をついばむと今度はその小鳥を狙って猛禽が現れたのです。
シッダッタ(お釈迦さま)は、自らの命を保つために、他の命を奪わねば、生きることが出来ない現実を、目の前で突き付けられ考え込んでしまいました。
生老病死
人は、年月とともに若さを保つことは出来ない。
やがて老いていかなければならない。
何人と言えども老いを避けることは出来ない。
又、その時健康であっても、いつまでも健康でいれるわけではない。
いつ病気や怪我をするかもしれない。
いくら丈夫な体を持っていても、あてにすることは出来ない。
そして、全ての命は必ず死を迎える。
誰一人と言えども、決して「死」を避けることは出来ない。人間、このような不安を抱えたままでは、せっかくの、この人生を精一杯生きることも、力を出し切ることも出来ない。どうすれば、この苦を超えることがで来るであろうか。
このことをずっと考え続けたシッダッタ(お釈迦さま)は、いつしか「出家」することを思うようになったのです。
こうしたお釈迦さまの心の軌跡を、仏伝では「四門出遊」の物語で伝えています。
| 四門出遊 シッダッタ(お釈迦さま)が、城の東門から出て老人に会い、南門から出て病人に、西門から出て死人に、北門から出て修行者に会ったことを機縁として出家した、と伝えられています。 |
又、苦悩の深さは、当時の「輪廻」という思想にあったとも考えられています。
「死」自体は恐怖であり、苦ではありますが、それは一度死ねばそのことは解放されます。
しかし、「輪廻」するということは、又、再度何らかに生まれ変わり、果てしなく死の恐怖を繰り返さなければならないということです。
シッダッタ(お釈迦さま)にとって、この輪廻からの解放こそが、苦悩の根源からの解放であると同時に、出家の大きな動機でありました。
結婚
マヌ法典では、学生期を終えると結婚し、息子をもうけなければならないと定めています。
結婚相手は、同じカーストの女性と結婚することが許されますが、その反対は許されませんでした。
当時のインドは、一般的に早婚でシッダッタ(お釈迦さま)の結婚も、17・18・19歳など諸説があります。
はっきり言えるのは、シッダッタ(お釈迦さま)は、20歳には結婚されていたようです。
仏伝では、お釈迦さまの妻としてヤソーダラー、ゴーピー、ミガジャーなどの名前が出てきますが、古代インドでは後継者をもうけることが家長の務めであり、そのためには複数の妻を持てることが認められていたようです。
シッダッタも出家するまでは、そのことに従ったかもしれません。
お釈迦さまの妻としては、息子ラーフラを出産したヤソーダラーが知られています。
このヤソーダラーは従妹でした。
お釈迦さまの出家~入滅

お釈迦さま出家 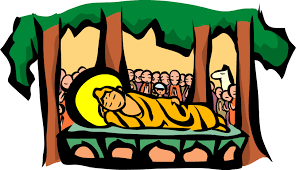
お釈迦さま入滅
出家
当時のシッダッタ(お釈迦さま)は、現在いかに幸福であっても、いかに美しい姿であっても、いかに裕福であっても、永遠に続くものではない。
どれほど多くの戦いに勝ち、たとえ世界の帝王となっても「死」を免れることは出来ない。
生滅変化を続ける現実。
決して避けられない死の壁。
輪廻の恐怖。
若きシッダッタ(お釈迦さま)には、どれ1つ解決の糸口が見えず、かといって投げ出すことも出来ない難しい課題があったのです。
その上、社会を支配していたカースト制度や、それを支える生活規範を定めた「マヌ法」の不条理さも、シッダッタに追い打ちをかけたのです。
職業は、その階級によって細分化され制限されていました。現在もこの定めは、形を変え生き続けています。
生活規範が事細かく定められ、バラモン、クシャトリアは特に、様々な規定に縛られていたのです。
このような状況に悩んだシッダッタ(お釈迦さま)は、出家します。
このシッダッタの出家は、通常の生活を棄てたことです。
不条理な社会制度・生活規範を否定したのです。
本来の人間の在り方の世界を求めたのです。
シッダッタ(お釈迦さま)は、生まれを問うのではなく、その行いを問う世界を希求し、そのために全てを棄てたのです。
シッダッタ(お釈迦さま)には、結婚十年ほどで、ヤソーダラーとの間に、息子ラーフラが生まれました。
これで、シッダッタには、出家できる条件が整いました。
息子ラーフラが生まれることによって、シャカ族を継ぐ後継者が出来たからです。
29歳になっていたシッダッタは、ある夜、従者チャンナを伴ってひそかに宮殿を抜け出しました。
シッダッタは、東方へ進み、コーリア国とマッラー国との境を流れる河を渡り、そこで剃髪をし、袈裟をまとって出家修行者の第一歩を踏み出したのです。
従者チャンナは、シッダッタの出家を思いとどまらせようと懇願しましたが「生と死との彼岸を見ぬ限り、再度カピラビャットゥの都には帰らない」と、従者チャンナを宮殿に帰しました。
という伝説が残るほど、シッダッタ(お釈迦さま)は出家を決意したのです。
修行
生れ故郷を出たシッダッタ(お釈迦さま)は、ガンジス河を渡り、当時、大国であったマガダ国の首都ラージャガハへと向かいました。
その当時のラージャガハは、北インドの政治・文化の中心で高名な宗教家・思想家が集まった都市でした。
シッダッタは、名声のあるアーラーラ・カーラマと、ウッダガ・ラーマプッタという二人の出家者に師事し、禅定の修行をしました。
シッダッタは、短期間で、アーラーラが体得していた境地に達し、又、ウッダガが体得していたのと同じ境地に達します。
しかし、シッダッタは、どちらの禅定も共に涅槃に達する道でないと知り、二人の師のもとを去りました。
| 涅槃 一切の苦から解放されることを「解脱」といい、その境地を涅槃と言います。 |
苦行
シッダッタは、二人の師につきましたが、二人の師の説く禅定の理論と実践に満足出来ませんでした。
そこで、シッダッタは、ラージャガハの西方、ウルベェーラーの森に入って、断食などのありとあらゆる苦行を試みました。
このネーランジャラーの辺りのセーナ村での苦行は、六年にも及びました。
シッダッタは、後に「如何なる者でも自分が行じたほどの激しい苦行をした者はいない」と回想しています。
その苦行は、文字通り骨と皮だけになってしまい、目はくぼみ、皮膚は黒く干からび、まさに骸骨のようなような様相を呈していました。
シッダッタが苦行をしていた際に、激しい苦行を共にしていた五人の修行者がいました。
この五人は、ウッダカのもとにいたとも、父王がシッダッタのために遣わしたとも伝えられています。
この五人は、シッダッタの激しい苦行に感動し、シッダッタがきっと悟りに達するだろうと、期待を込めて見守っていました。
しかし、シッダッタは、身体をいくら苦しめても心の平安は得られませんでした。
シッダッタは、現在の自分が行っているのは、「苦行の為の苦行」であって、悟りへの道ではないとい気づきはじめていました。
精神と身体とは、別物ではない。
身体が滅びる時、精神も機能しなくなる。
死んでしまっては何の意味もない。
生きているからこそ、悟ることが必要なのだ、との考えに至りました。
そう気づくとシッダッタは、苦行を棄てる決意をして、ネーランジャラー河で汚れた体を洗い、心身ともに一新して岸に上がろうとしましたが、あまりにも衰弱がひどく、容易に上がることが出来ませんでした。
シッダッタは、木の根にしがみつき、ようやく岸に這い上がった時、セーナ村の村長の娘スジャータが通りかかり、あまりの状態を見かねて乳粥を捧げました。
シッダッタは、その乳粥を胃に流し込むと、生命力がよみがえってくるのが分かりました。
この様子を見た五人は、「彼は堕落した」とみて、シッダッタを見捨て、ベナレスへと去っていきました。
スジャータの捧げた乳粥を食し、生気を取り戻したシッダッタは、アシバッタ樹の下に座し瞑想に専念しました。
成道
アシバッタ樹下での禅定によって、悟りに至ったお釈迦さまを仏伝には、「降魔成道」の話として語り伝えています。
悪ナムチの強迫や誘惑に惑わされず、その魔を降伏させたと伝えられているのは、悟りをはばむ魔との闘いであり、それは自己自身との闘いを意味しているのです。
利益・名声・社会的地位など一般的にはこれらの誘惑に負けてしまうことが多いのですが「自分はきっと勝ってみせる。
誘惑に負けて苦の世界で生き延びるようなことはしまい、如何なる誘いであっても、きっと禅定の叡智で超克してみせる。」
このような強い決意で臨み、ついに内なる煩悩を克服し、もはや輪廻に縛られることなく、完全に開放された境地に至り、「我は仏陀(真理に目覚めた者)となれり」と、シッダッタ(お釈迦さま)は、宣言したのです。
この時、お釈迦さまは35歳でした。
悟りを開いた人を「仏陀」と言いますが、そのお釈迦さまの開かれた所をブッダガーヤーと呼ばれ、アシュバッタ樹は、その下で菩提(悟り)を得たことから「菩提樹」と呼ばれるようになりました。
お釈迦さまの悟りの内容を「縁起」と言います。
相互に依存して存在する関係や相互に依存して生滅する関係を「縁起」と言います。
「苦」の根本原因は「無明」である。
無明とは、人生の信実相に関する「無知」である。
自分の都合でしか物事を見ていないので、真実の姿が分からない。
自分の都合だけで物事を見て思い通りにならないと言って苦を招いたり、更に欲の心をおこして苦を深めていく。
言い換えれば、無明を滅すれば苦悩も滅すると教えられています。
伝道
インドでは4~5月は最も暑く、6月に入ると雨期に入ります。お釈迦さまは雨期には遊行せず、雨期以外の時期に各地を遊行して教えを伝えられました。
指導的立場の人を論破し、教えを伝え、お釈迦さまの教団は増大していきました。
入滅
お釈迦さまは、80歳になっても旅を続けられていましたが、クシナーラで最期を迎えられたのです。
お釈迦さまは、仏陀となり、45年間法を伝えられましたが、沙羅双樹のもと、頭北面西右脇に臥して入滅されました。